2012年08月30日
【メモ】アトピーについて
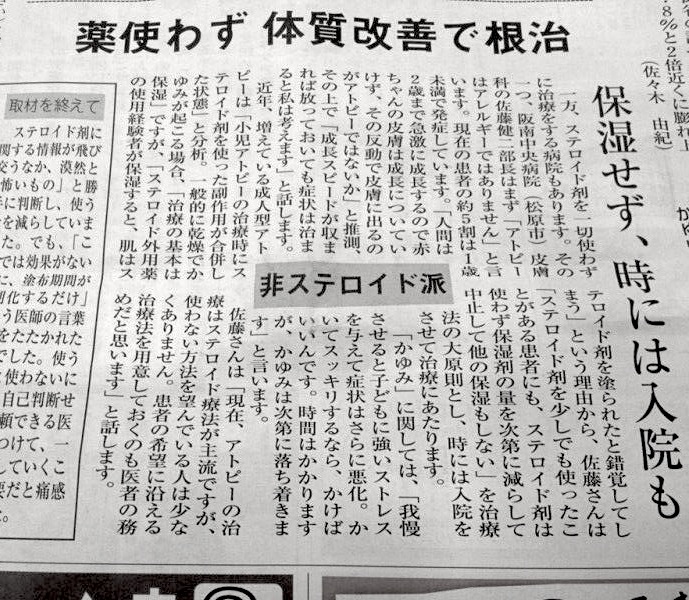
佐藤健二先生
阪南医療福祉センター 阪南中央病院
http://www.hannan-chuo-hsp.or.jp/
「成人型アトピー性皮膚炎」の治療上の工夫
http://atopy.info/essay/7.html
患者に学んだ成人型アトピー治療―脱ステロイド・脱保湿療法
http://atop.happy-lucky.biz/index.php?佐藤健二先生#h2671e88
●成人型アトピー性皮膚炎とは?
「成人型アトピー性皮膚炎」とは、ステロイド使用によって生じたステロイド依存性皮膚症を合併するアトピー性皮膚炎で、そのほとんどの患者は保湿依存症を伴います。ステロイド依存性皮膚症とは、皮膚が外用ステロイドなしには普通に機能しない状態で、外用中止により離脱症状を起こします。保湿依存症とは皮膚を保湿しないと一定の状態を保持できず外用ステロイドの離脱症状と同様の症状を起す状態です。
●脱ステロイド脱保湿とは?
脱ステロイドとは、薬物として外用された化学物質としてのステロイドが皮膚から除去されることと、ステロイド外用により生じた種々の皮膚調節機構の撹乱(ステロイドの影響)が元に戻ることを意味します。
前者は約一ヶ月で完了するが後者はかなり長期(数年)にわたることが多いです。脱保湿とは、水分が常に過剰に皮膚表面に人工的に存在させている状態をなくすことと、この状態に適応した皮膚の代謝過程から、皮膚が普通に大気に接している状態での皮膚の代謝への変換を意味します。
前者はすぐに可能ですが後者は脱ステロイドと同じく長期にわたることがあります。
ステロイド依存症からの脱却には脱ステロイドと脱保湿が必要です。
●脱ステロイド初期の皮膚状態
脱ステロイドあるいは脱保湿を始めて一週間ほどは非常につらい時期です。特に重症の人では、全身の皮膚は赤みを増し、腫れ、滲出液が出、亀裂があり、痂皮により皮膚が突っ張り、激しい痒みが続き、夜は眠れず、昼もしんどくて布団から出るのがつらいという状態が続きます。
皮膚の毛細血管は透過性が亢進し少しの変化で血管内の水分が外に出る状態となっています。出ると浮腫が起こり、表皮側に障害があると簡単に皮膚の外に水分が出て行くことになります。血管透過性が亢進する理由は、炎症によりヒスタミンが出ることでも起こりますが、血圧が上昇することでも起こってきます。
●水分摂取の調節が重要
脱ステロイド初期には理由は未だ不明ですがのどの渇きが強くなります。必然的に水分を多く取ることになります。皮膚の状態にもよりますが、症状がよりひどければより容易に皮膚の表面から滲出液が出たり、水分蒸発が起こります。
のどの渇きに従って水をがぶ飲みすると、血管内の水分量が増え血圧が上がり血管からの漏出が増えます。また、水分を多く取ると血管内の浸透圧が減少し相対的に透過性が亢進します。従って、脱ステロイド中は水分の摂取には注意をし、摂取過多にならないように注意することが必要です。
ひとつだけ重要な注意をしておきますが、水分を取らなければ取らないほどよいと思わないことです。水分は一日に2500mlほど必要です。水分をあまり取らないようにすると血液中のナトリウム(塩分)濃度が高くなりすぎて命にかかわることがあります。
だから、重症の人は医師の監視の下に脱ステロイドをするほうが安全です。
何らかの理由で体温が上がり38度を超えることになれば水分調節(制限)は中断し、のどの渇きに従って水分を自由に摂取する必要のあることも知っておくべきことです。
脱ステロイド初期の激しい症状が良くなり安定した状態になった時点で水分制限が必要かどうかという問題は、次のように考えています。
安定した時期には水分制限は必要です。その後、皮疹がほとんど消失した時点では水分制限はあまり厳しく監視する必要はありませんがどちらかというと少し水分控えめ程度が安全です。脱ステロイド後も時々皮疹の悪化するときがあります。このときには水分制限は再度重要な注意事項となります。
よく多くの水を飲んで体の毒素を洗い流すという発想で水を大量に飲む方がおられますがこの考えは捨てたほうがいいと思います。
「保湿ってよくないの?」
わかりやすいので引用させていただきました。
http://ameblo.jp/miko-choco/entry-10408568457.html
☆脱保湿!!!保湿力をつけるためには、手をかけないこと!
1)保湿剤等
肌に塗る軟膏やクリーム、オイル、化粧水は使用しません。
脱ステ、脱プロと同時に脱保湿も行います。
ワセリン、アズノールクリーム、亜鉛化軟膏、馬油、自然派化粧水等もほぼ使用しません。
例外として、貨幣状湿疹等の皮疹や部分的なビランに一時的に亜鉛化軟膏を使用する場合があります。
通常は脱ステと同時に脱保湿を行いますが、既に脱ステ済みで症状が軽減しない場合や数年後に悪化したような場合は後から脱保湿のみ行うパターンもあります。
長期に渡りステロイドを使用してステロイド依存となっている皮膚の場合は、同時に保湿依存となり皮膚が正常に機能しない場合が多々あり、そういった皮膚の場合は脱保湿により乾燥を促し、自然に自身の皮脂を出す方向に持って行く事で改善する事が多い為、脱保湿を重要としています。
2)お風呂やシャワー
お風呂やシャワーも同様に皮膚を保湿する事になります。
その為、基本的には入浴時間もシャワーを当てる時間も短縮します。
どちらも3分程度を目安に、症状によってはより肌が水に触れる時間を少なくするようにします。
感染症の心配があるビラン状の皮膚の時は石鹸を使用し軽く流します。
ビランが無くなり皮膚が乾燥して来た時期には、汚れの気になる部分以外は石鹸を使用せずに水で流す程度にしたり、1日置きの風呂やシャワーとする等、患者や症状により調整します。
この時の水温は出来るだけ低いのが望ましく、夏は水、冬はぬるま湯が良いとしています。
3)温泉
温泉もリラックス効果がある反面、保湿効果が高い為、脱保湿中は禁止としています。
皮膚が正常化して安定した場合は、自己管理しながら短時間から試してみるのは可能としています。
4)布団
就寝時の布団については、掛け過ぎて保温し過ぎると、体中が蒸れて同時に全身の保湿になるとしています。
布団をめくった時に湯気や熱気が出るようなら掛けすぎの為調整します。
また、脱ステ時の体力消耗や不眠から昼寝をする場合も布団にくるまり眠るのは1日の大半を全身保湿する事に繋がる為禁止とされています。
昼間眠る場合は、椅子に座って眠ったり、ベッドを起こして布団に入らず仮眠を取る程度が良いとしています。
5)包帯やタオル等での皮膚の保護
脱保湿中は、皮膚を出来るだけ湿らせないように、蒸れないようにして乾燥を促す事を基本としています。
とは言っても乾燥による皮膚の捲れや亀裂は自身の微動によって起こる空気の流れも凍みる程痛いもの。
その場合は、包帯をグルグル巻かずにガーゼを患部にひと巻きする程度に保護し、通気性も同時に保つようにとしています。
腹巻き、タイツ、タオルでの首の保護も同様に保湿になるとしています。
しかし、例外として、多少保湿になっても掻き壊し防止の為に皮膚を被い保護する場合があります。
これはそれぞれの症状等によっても違う為、基本方針から外れて様子を見ながら試してみる事になります。
6)保湿石鹸等の使用
入浴時の石鹸やシャンプーは、潤い成分の入っていないものを勧めています。
先生の治療では、基本的には牛乳石鹸青箱とメリットを用います。潤い成分の入っていないシンプルなものであれば代用は可能。
7)化粧
顔の皮膚が正常化した場合、女性の場合は化粧がしたくなるものですが、原則禁止としています。
特にファンデーションで顔を覆う事は粉の下に水分や皮脂が溜まり、保湿に繋がるとしています。
例外として唇は粘膜なので多少の保湿では悪化しない。
佐藤先生の元で脱ステをした人も、症状が安定した場合は基礎化粧品や通常の化粧品を使っている方もいますし、先生の著書でも皮膚の状態が安定して、どうしても化粧が必要な場合は、2~3日程度から試験的に保湿や化粧を試すという方法が記載されています。
但し、ステロイド依存や保湿依存が長期化して皮膚の萎縮が激しかった場合等は特に、化粧品を使用する事によって保湿が促進され、赤みが出る事が多い為注意が必要です。
これは、皮膚の細胞に残る『ステロイド依存や保湿依存の際の細胞記憶』によるものとしています。
☆睡眠薬を使ってでもちゃんと寝て、朝から活動する!
1)脱ステ時の不眠対策に使用。
脱ステ時には頻繁な離脱と皮膚再生を繰り返します。
最初は重い離脱と緩やかな皮膚再生を長いサイクルで繰り返し、後に軽い離脱と急速な皮膚再生を短いサイクルで繰り返します。
この離脱から皮膚再生への効率の良い移行と、正常な皮膚に早く戻して行く為には睡眠が重要です。
また、良質な睡眠と起床後の生活という1日の生活バランスも大変重要としています。
生活リズムを正して体の機能を正常化していく為にも、夜は十分に眠り、朝は起きて行動をするという治療方針に基づき、脱ステ中は睡眠薬を使用する場合が多々あります。
但し依存性がある為、症状が軽減して睡眠が取れるようになって来た場合は、ゆっくりと減らし止めて行く方針です。
■掻く事に対して
1)掻く事に対して罪悪感を持たない事。
脱ステ時の痒みは我慢出来るものでは無く、我慢しようとする事でストレスにも繋がる為、周囲も「掻くな」とは言わない事。
掻いても少しずつ強い皮膚になり、最終的には掻いても傷が付かないようになる為、掻いても良い。
■滲出液対策
1)滲出液には皮膚再生に必要な良質な蛋白質が多く含まれているので拭き取らない。
2)特にティッシュには化学物質が多く含まれる為、ビランになり滲出液が出ている患部に当てない。
3)滲出液が流れ出る場合はガーゼで軽く抑え、ガーゼ1~2枚を貼り付けておく。
貼り付かない場合は何も当てる必要は無く患部の通気性を保った方が良い。
4)顔や頭、耳等の滲出液が多い場合は、就寝時ベッドの頭部側の高さを上げる。クッション等を重ねて調整しても良い。
5)水分摂取過多の場合は滲出液が増える為、適宜制限をして調整する。(後述)
■水分制限
1)滲出液対策として水分制限を行う。
脱ステは滲出液を伴ったり頻繁に落屑を繰り返すが、これにより体内の蛋白質も多量に流出する。
正常な皮膚の再生には蛋白質が大変重要だが、過剰な水分摂取により滲出液が増えて止まらなくなるると蛋白質の流出も進み皮膚の再生も停滞する。
症状の悪化により喉が渇いたり、食欲が減退して固形物より流動物を欲したりと、余計に水分摂取過剰となり悪循環になりやすい。
この連鎖を絶ち、滲出液の増加を抑え、皮膚乾燥させて正常に再生させる為に水分摂取制限が必要。
2)入院治療では、食事に含まれる水分を除き『日常で摂取する水分量』を1200~1500mlとする。
体重や気温、発熱状態によって異なるが通常は1200ml程度が妥当。
気温の高い夏に汗をかいた場合はその分を増やし、冬は減らして調整する。
発熱した場合も同様に増やす。目安として38度を超える発熱の場合は制限を無くして水分摂取が必要。
3)この水分計算では、食事として摂る『味噌汁』や『牛乳』、『野菜やごはんに含まれる水分量』は計算に入れないが、間食として摂るドリンクや、ヨーグルト、プリン、フルーツ等の流動物は『日常で摂取する水分量』として計算する。
4)個人での水分制限(入院以外で独自で行う水分制限)は、食事に含まれる水分計算が難しい為、喉の渇きや尿の色で判断する。
一度にゴクゴクと飲まず、間隔を空けて少しずつ飲み、多少喉の渇きを残す程度の摂取が望ましい。
尿の色は透明に近いと水分摂取過多の可能性が高い為注意する。
5)脱ステ直後は、電解質バランスが狂い高ナトリウム血症となる場合もあるが、この時は無理な制限をせずに多少制限を緩めて水分摂取する事も必要。
高ナトリウム血症の症状としては、頭がぼぉっとしたり異常な喉の渇きが起こる事があるが、正確には医療期間
で血液検査をして、ナトリウムが正常値か確認が必要。
6)滲出液が減り皮膚が正常になって行くと喉の渇きがおさまる場合が多い。
この時期になると、多少水分を摂りすぎても滲出液や炎症として皮膚表面に出ない事が多い。
■蛋白質摂取
1)脱ステ時期には滲出液や落屑が増え、皮膚の再生の為に必要な蛋白質が体外に流出しやすい為、積極的に蛋白質摂取する事が必要。
2)摂取する蛋白質については、動物性、植物性問わずバランス良く摂るのが良い。
納豆、豆腐、大豆、豆乳、牛乳、ヨーグルト、チーズ、肉、魚等があるが、塩分や水分の含有量に注意する。
■食事制限
1)基本的には食事制限はしない。
何でもバランス良く食べ、栄養を摂る事が重要。
自覚症状として明らかにアレルギーのある食品は各自で制限をする。
2)皮膚に悪いとされる嗜好品についても過剰な制限をしない。
砂糖や甘いお菓子等も、バランス良く食事を摂った上で、たまに食べる事に関しては問題無い。
コーヒー、アルコールに関しては、痒み成分も含まれるがリラックス効果もある為、試してみて痒みを強く感じる場合は控え、リラックス効果により痒みを忘れる場合は適度に摂っても問題は無い。
■規則正しい生活
1)脱ステ中は、痒みや痛み、不快感より不眠が起こりやすく、朝方眠り昼に起きる等、昼夜が逆転している場合がある。
昼夜が逆転していると症状の改善が遅い場合も多い為、生活リズムを正す事が重要。
睡眠薬を利用してでも夜は眠り、朝は起きる事、規則正しく食事をして、昼間は身の周りの掃除や運動等で体を動かすように意識する。
また、掻かない為に夜眠らずに起きているという人も多いが、掻いても夜眠った方が皮膚の改善が早い。
■運動
1)運動する事により血行が良くなり、皮膚症状の改善に効果が見られる為、治療の一環として勧めている。
脱ステ初期の場合は滲出液が多かったり亀裂が入り痛みや消耗も激しい為、そのような場合は無理をせずに休息を取り、最初は疲れない程度の軽い運動から始める。
2)具体的には、『休まず30分程度の早歩き』で良い。
休まずに早歩きする事で有酸素運動となる為、ゆっくり長期間歩くより効果的である。
■食事は何を食べてもいい
多くの人は、アトピー性皮膚炎患者は食物アレルギーがある、と信じていています。しかし、この信念は間違いです。食事は何を食べてもいいのです。
甘いものでも、油っぽいものでも、お菓子でもかまいません。食物アレルギーが本当にあれば医師を訪れる前に患者本人あるいは家族が発見しています。勿論当たり前の話ですが、自分で発見しているアレルギー物質を食べるのはもちろんだめです。
要するにバランスよくお菓子などは食べ過ぎないようにすればいいのです。アトピー性皮膚炎でつらい思いをしているのに、更にあれを食べたらだめこれを食べたらだめといわれたら本当にかわいそうです。アレルギー検査をして陽性に出ても、検査までに食べていたら何の制限も要りません。
■お風呂は消毒の変わり
まだイソジン液で体を消毒する治療方法が行われています。褥瘡や皮膚潰瘍に対する治療として消毒薬を使う消毒は行わなくなってきています。消毒薬の細胞障害性が皮膚の治癒を遅らせるからです。
脱ステロイドをするときには、皮膚は細かく見ると小さな傷がたくさんあります。イソジンはこの傷に悪い作用を及ぼします。細菌を殺すとして使われている超酸性水も同じ理由で使わないほうがいいのです。その代わり、お風呂で優しく皮膚を洗えば、皮膚の細菌を洗い落とすことにより感染予防になり、細菌増殖の温床である痂皮などを取り去ってくれます。
強く洗うことは避けるべきですがお風呂は脱ステロイドを順調に進ませるために積極的な意義があります。なお、石鹸はアトピーに良いとか肌に優しいとか言われているものは避ける必要があります。保湿作用があるからです。なお入浴は短時間にすべきです。15分ぐらいが適当です。
皮膚がかなり強くなると、入浴は心臓を強くするためのリハビリとしても利用できます。このときは、注意さえしておればかなり長時間はいっても問題はないでしょう。
ーー
【皮膚表面に現れるさまざまな病変の医学用語】
アトピー皮膚:
紙のように薄くなり、しわがよった皮膚。
痂皮(かひ):
皮膚の表面で血や膿、体液が固まったもので、俗に「かさぶた」という。皮膚の傷ついた部分にできる。
びらん:
皮膚の表層の一部またはすべてが欠損した状態。感染、圧迫、刺激、温度などによって皮膚が損傷を受けると、びらんが生じる。
擦過傷(さっかしょう):
皮膚がえぐれたり、線状にかさぶたができた状態。皮膚をひっかいたり、こすったり、突いたりしたときに生じる。
苔癬化(たいせんか):
皮膚が厚くなり、表面にしわや溝が深くくっきりと現れた状態。皮膚を長期間ひっかくことで生じる。
斑(はん):
皮膚の表面にできるさまざまな形をした、直径約10ミリメートル未満の平らな変色部分。そばかす、平らなほくろ、ポートワイン母斑、各種の発疹などが斑状となる。これより大きなものはパッチと呼ばれる。
結節:
硬く盛り上がったしこりで、丘疹よりも深くはっきりと感じられる。表皮の下にできた結節が、皮膚を押し上げているように見えることがある。
丘疹:
直径約10ミリメートル未満の硬く盛り上がった病変。いぼ、虫刺され、スキンタグ、ある種の皮膚癌などが丘疹となる。
局面(プラーク):
皮膚から平らに盛り上がった隆起やその集合体で、通常は直径が約10ミリメートル以上。
膿疱(のうほう):
膿を含んだ水疱。
鱗屑(りんせつ):
死んだ表皮細胞が蓄積し、カサカサに乾燥した斑状の病変。うろこ状になり、はがれて落屑を起こしやすい。乾癬、脂漏性皮膚炎などでみられる。
瘢痕(はんこん):
正常な皮膚が線維状の組織で置き換わった状態。真皮の一部が破壊されると生じる。
毛細血管拡張:
皮膚の内部で血管が拡張し蛇行しているのが透けて見える状態。圧迫すると白くなる。
潰瘍(かいよう):
びらんに似た病変で、深さが少なくとも真皮の一部にまで到達しているもの。びらんと同様の原因でできる。
小水疱:
直径約5ミリメートル未満の、中に液体が詰まった吹き出もの。より大きいものを水疱という。虫刺され、帯状疱疹、水ぼうそう(水痘)、やけど、炎症などによって小水疱や水疱ができる。
膨疹(じんま疹):
軟らかく盛り上がったスポンジ状の腫れで、皮膚の表面に比較的急に現れ、やがて消えてなくなる。薬、虫刺され、何らかの物質の皮膚への接触に対する一般的なアレルギー反応として生じる。
Posted by タナカミサト at 10:33│Comments(0)




